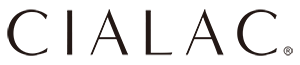子供に料理のお手伝いをしてもらうコツやメリット|年齢別にできることも紹介
子供の成長のために料理のお手伝いをしてもらいたい親は、多いのではないでしょうか。また、親が料理をする姿を見て自分から興味を持つ子供もいます。しかし、仕事や家事が忙しく、子供と一緒に料理をする余裕がない方もいるでしょう。
料理のお手伝いをしてもらうと、コミュニケーションが取れるだけでなく、子供の心身の成長にもつながります。この記事では、子供に料理のお手伝いをしてもらうメリットのほか、コツや注意点、子供にできることを解説します。どのように子供にお手伝いをしてもらえば良いか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
子供が料理のお手伝いをする7つのメリット

お手伝いをしたいと子供から言われても、料理を教えたり、作業する様子を見守ったりする余裕がなく、なかなか実現できないことはあるでしょう。しかし、料理のお手伝いをしてもらうことは子供の成長につながるなどの、さまざまなメリットがあります。
1. 脳に刺激を与え成長を促す
料理のお手伝いは、子供の成長を促すのに役立ちます。料理には細かな作業があるため、手先を継続的に使うことで、脳の活性化につながります。東京都教育委員会の資料によると、子供の脳内の神経のつながりは、生後の環境から与えられる刺激に左右されることがわかっています。特に五感から入る刺激は脳に直接伝わり、影響を与えるのです。
料理中は手先を良く使うことで触覚を刺激するほか、嗅覚や聴覚もはたらきます。食材を切るときの「トントン」や、肉を焼く「ジュージュー」といった音も、脳への刺激のひとつです。
2. 味覚を鍛えられる
お手伝いを通してさまざまな食材に興味を持ち、積極的に食べるようになることで、味覚が鍛えられます。
食べ物の味を感じる舌の表面にあるブツブツ「味蕾(みらい)」は、大人になるにつれ減っていくといわれています。味蕾の多い子供のうちに、さまざまな素材の味を体験することで味覚の幅を広げることができます。その時期に料理のお手伝いをすることで、味見などを通して味覚を鍛えることができるでしょう。
3. 好き嫌いが減る
食べ物の好き嫌いがある子供は少なくありません。しかし、食べるだけではなく、自分で料理を作ることで、好き嫌いを減らすことにつながります。
自分で料理をしたという達成感から、これまで食べなかったものへも挑戦できるようになるでしょう。さらに、自ら作った料理には愛着が湧くため、普段より美味しく感じるものです。
4. 段取りができる
料理のお手伝いをすると、工夫することを覚え、段取りができるようになります。料理を作り始めてから完成するまでには、下ごしらえや調理、盛り付けなどさまざまな工程があるからです。
たとえば、食材に味をなじませる必要があるなら先に準備をしたり、鍋に火をかけている間に他の作業をしたりします。始めはスムーズにできなくても、大人のやり方を見ながら、学んでいくでしょう。そのため、料理のお手伝いを続けると、自分で考え工夫し、段取りができるようになります。段取りをする力は、子供が幼稚園や保育園、学校での生活をスムーズにおくるうえでも大事な要素です。
5. 自信がつく
お手伝いをして褒められると、認められたと感じ、子供の自己肯定感が高まって自信がつきます。
なかでも、自分でやったという達成感を感じられるお手伝いは、自信につながりやすいです。たとえば、味見をしながら味噌汁に味噌をといていく作業は、味を決めるメインの工程のため、達成感を得られやすいでしょう。また、はじめは上手にできなかった作業が、お手伝いの回数を重ねるごとにできるようになっていくと、自信がつくものです。料理のお手伝いは、子供の自信を高めるのに役立ちます。
6. コミュニケーションが取れる
料理のお手伝いをしてもらうと、親子での共同作業となるため、コミュニケーションが増えます。親とのコミュニケーションが増えれば、子供の心も満たされます。
また、会話を楽しむだけではなく、料理中にやってはいけないことや危険なことなどを子供にしっかり伝えることも、大事なコミュニケーションのひとつです。日々のお手伝いを通じて、意思疎通がより図りやすくなるでしょう。
7. 感謝できるようになる
料理のお手伝いは、家族のためにすることが多く、誰かの役に立てた喜びを感じるようになります。それに伴い、普段、親が料理を作ってくれることに感謝できるようになるでしょう。
人への感謝の心を育てるには、その物事の大変さを知ることが大事です。料理のお手伝いをすることは、その第一歩となります。
子供に料理のお手伝いをうまくしてもらうコツ

子供はさまざまなものに興味を持ちますが、飽きるのも早く、継続するのが難しい場合があります。ここでは、子供に料理のお手伝いをうまくしてもらうコツについて解説します。
褒める
料理は楽しいものと子供に覚えてもらうには、笑顔で接し、小さなことでも褒めることが大切です。手伝ってくれたことに「ありがとう」と親から伝えると、子供からも前向きな言葉が出るようになります。
お箸を並べたり、野菜のヘタをとったりするような些細なことでも、できたら褒めましょう。褒めると子供のやる気がアップし、継続して手伝ってくれることが期待できます。
最後まで子供を見守る
親が途中で手出しをせず最後まで見守ると、達成感や満足感があり、「またやってみたい」と子供は感じます。たとえば、卵を割ってもらう場合、器に殻が入ることもあるでしょう。その場合でも、殻を取るところまで子供が行う姿を見ていることが大切です。
親が手伝ってしまうと、子供のやる気を削ぐことにつながる可能性があります。料理のお手伝いを続けてもらうなら、最後まで子供を見守るようにしましょう。
余裕があるときにお手伝いしてもらう
子供にお手伝いをしてもらうと、失敗したり、時間がかかったりすることがあります。時間がないときにお手伝いをしてもらうと、ストレスを感じてしまうこともあるでしょう。
お手伝いしてもらうなら、時間がかかっても大丈夫なときや、余裕のあるときがおすすめです。
お手伝いをしてもらいたいけれども、時間の余裕がない場合は、失敗しにくいことをお願いしてみるのもひとつの方法です。たとえば、一緒に食材を買いに行くことや、レシピ本でメニューを選んでもらうことなどが挙げられます。
子供用の料理グッズを利用する
子供用の料理グッズを使うと、楽しみながらお手伝いできるため、習慣化しやすくなります。子供用の包丁やピーラーを使ってみましょう。ただし、子供用とはいえ包丁を使う際には目を離さないことが重要です。
また、場所選びもお手伝いを継続してもらうには大切です。キッチンは大人用の高さになっており、子供にとっては作業しにくいでしょう。その点、ダイニングテーブルなら、椅子の高さを調整しながら、子供の背丈に合わせられます。材料を切ったり混ぜたりする工程は、ダイニングテーブルのように高さを調整できる場所で行うのがおすすめです。
子供に料理のお手伝いをしてもらう際の注意点

料理のお手伝いは、子供の心身の成長にもつながります。ただし、失敗しやすいポイントを知らずに始めてしまうと継続できない場合があるので、お手伝いをしてもらう際の注意点を押さえておきましょう。
怒らない
子供は褒められるとさらに頑張ろうとしますが、怒られるとお手伝いが楽しくないと感じ、継続できなくなってしまいます。
子供が行った作業を、本人の前で親がやり直すことも避けましょう。子供の自尊心が傷つき、自信をなくし、進んでお手伝いができなくなるケースもあります。できなかったら教え、一緒にやってみることが大切です。
飽きたら止める
子供は飽きっぽいので、自分から「やりたい」と言ったにもかかわらず、お手伝いの途中でやめてしまうこともあります。そのときに無理強いをしないことが重要です。
年齢を重ねると、できることや集中する時間が増えるため、その都度やりたいことをやってもらい、お手伝いは楽しいものと理解してもらうのが良いでしょう。ただし、ふざけはじめた場合には怪我につながる可能性があるため、すぐに止めることも大切です。
強制しない
嫌なことをしてもらっても継続できないため、強制しないことが大切です。やりたくないことをしていると、お手伝いは楽しくないものと思ってしまい、続かないことがあります。
興味がないと子供は動かないため、料理のお手伝いをしてもらうには、関心を引くことが大切です。たとえば、果物が好きな子供には「りんごをお皿に乗せて」と興味を示すことをしてもらいましょう。
怪我につながるものに気を配る
子供に料理のお手伝いをしてもらう際には、包丁を使って怪我をしたり、火に触れて火傷したりしないように気を配りましょう。怪我をしないためには、子供が包丁を使いやすい場所で行うことが大切です。例えば、背の低い子供に合わせてダイニングテーブルや踏み台を使うと良いでしょう。
包丁を使う際は、「刃を触ってはダメ」と使う前に説明することが重要です。包丁の持ち方や猫の手のほか、食材を切るときは上から下へ包丁を下ろすこと、自分に向けて刃を向けないことなどを教えます。実際に食材を切るときは、怪我を避けるため、子供には触れずに見守りましょう。
火を使うときも、子供が使いやすい場所で行うことが、火傷をしないポイントです。火を点けたり消したりするのは親が行い、鉄やステンレスが熱いことを伝えましょう。
【年齢別】子供にできる料理のお手伝いの具体例

具体的にどんなことを手伝ってもらえば良いか分からない方は、多いのではないでしょうか。ここでは、子供にできるお手伝いの内容を年齢別に紹介します。
4歳までのお手伝い内容
4歳までの子供ができるお手伝いには、以下のようなものがあります。
- お箸やスプーン、フォークを並べる
- ご飯やおかずをテーブルに運ぶ
- 一緒に買い出しにいく
- レシピ本を眺め、メニューを決める
- トマトのヘタをとる
- 野菜や調味料を混ぜる
まずは、子供が好きなことや得意な内容から、お手伝いを始めるのがおすすめです。興味があることをしてもらうと、お手伝いは楽しいものと理解してもらいやすくなります。親が手を出さず、最後まで自分で行うと満足度が上がります。
5歳以上のお手伝い内容
5歳以上の子供ができるお手伝いには、以下のようなものがあります。
- ハンバーグのタネをこねて成形する
- 野菜を切る
- 盛り付けをする
- ご飯を炊く
- ご飯をよそう
- 火を使った料理をする
5歳以上になると、包丁や火を使ったお手伝いもできるようになります。お箸を並べたり、ご飯をテーブルに置いたりするような単純作業ではなく、調理の一部をすることで親の助けとなる場面が増えるでしょう。
継続していくなかで子供が責任感を持つようになり、お手伝いで自分の役割を果たそうとします。それが結果として、子供の成長にもつながるのです。
料理のお手伝いを通じて子供の成長を促そう
子供に料理のお手伝いをしてもらうと、脳が活性化したり、好き嫌いがなくなったりなど、さまざまなメリットがあります。お手伝いを習慣化するには、些細なことでも褒めることや、子供用の料理グッズを使うのが効果的です。
料理を楽しく作り終えたら、その後は片付け。料理をした後の片付けを効率的に行うには、ディスポーザーの設置を検討してみてはいかがでしょうか。ディスポーザーは生ごみを粉砕して下水道に流せる設備で、ごみを処理する手間を減らせます。
ニッコー株式会社のディスポーザーCIALACなら、オートクリーニング機能が付いているため本体に汚れが残らず、臭いも気になりません。自動ブレーキ搭載により、運転中に蓋を開けても安心なので、子供と一緒に片付けが行なえます。
また、CIALACは、ニッコー株式会社がPanasonic(パナソニック)社のディスポーザー特許を公式に取得して製造している、日本製のディスポーザーです。埼玉県にあるニッコーの自社工場で製造し、東京圏のディスポーザー付き新築マンションの4割程度でご採用いただいています。※2024年3月末時点で採用率38.7%(2023年度中に東京圏の新築マンション向けに出荷されたディスポーザーに占めるCIALACの割合)ご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ディスポーザーについて、
お問い合わせ、ご相談はこちら
法人の方もこちらからお問い合わせください
【参照サイト】東京都教育委員会
【参照サイト】pal system 子どもたちの五感を開く“味覚”の役割
【参照サイト】 日本経済新聞:3歳までが勝負 子どもの味覚の育て方